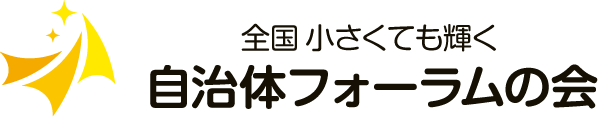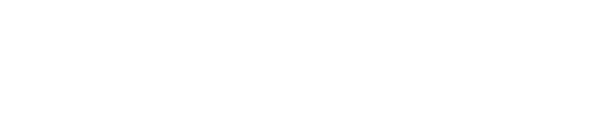新型コロナウイルス感染症の災禍をどうにか乗り越えたようにみえる現在、新たな危機としての戦争による災禍がヨーロッパ大陸や中東などで続いています。憲法の前文にある「平和的生存権」の保障を追求して確かなものにしていくことが、日本をはじめ世界中で求められています。
令和6(2024)年の初夏、私たちは、平和の基盤を支えている地方自治を充実させつつ、自律をめざす小規模自治体の維持と発展をはかることをめざして、宮崎県木城町に集いました。木城町は、「鉄道ない!国道ない!ないないの町で、僕も生きる!」を掲げながら、「人が元気、地域が元気、住んで良かった」を実現できる町づくりを町民参加で豊かに実践しています。その木城町を含む宮崎県の町村の魅力的な取り組みと、小さくても輝く町村を創造的に築いてきた全国の取り組みを、参加者相互に交流し、学びました。
今回のフォーラムでは、小規模町村の自治を取りまく新たな2つの動きが指摘されました。1つは、現在第213回国会で審議中の、「地方自治法の一部を改正する法律案」の「第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例」において、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」であれば、個別法の根拠規定がなくとも、国の地方公共団体に対する指示権を認める内容が盛り込まれていることです。これは、地方分権に逆行し、団体自治を侵害するものです。むしろ緊急事態においてこそ、徹底した分権化を図って、自治体が司令塔になって第一義的に事態に対処する「危機管理の現場化・地域化」が大切です。
もう1つは、10年前の「消滅可能性都市」論の再来ともいえる『令和6年・地方自治体「持続可能性」分析レポート』(2024年4月24日公表)が、人口戦略会議から出されたことです。「若年女性人口の減少率が 2020 年から 2050 年までの間に50%以上となる自治体」を「消滅可能性自治体」として、それが744自治体だというものです。これは、人口減少対策は国の社会保障政策などが鍵を握っているのに、それを市町村の責任に委ねて、市町村再編を促す新たな動きだと危惧されています。このような「集権化の荒波」に飲み込まれないためには、強いられた人口獲得競争から脱却して、住民の生活の質を向上させるために、地域ごとに一人ひとりの声に耳を傾けながら丁寧に施策を進めていくという市町村の本分に立ち返って、小さいからこそ、1人ひとりの住民が輝けるまちづくり・むらづくりを進めていくことが大切だと指摘されました。
今回のフォーラムの分科会でも、「有機農業・環境保全型農業と地域づくり」、「元気な集落づくり~定住対策・集落再生」、「学校を核とした地域づくり」といったテーマで学習と交流が行われました。シンポジウムでは、「ムラの未来を支える地域の誇り」を持ち続けることが大切で、持続的で豊かな地域経済・社会は、住民と自治体や住民同士の「対話」が日常的に行われていて、地域を担う主体が育成されることで「創れる」ものだといわれました。
現在は、時代と地方自治の転換期の中にありますが、小さくても輝く自治体の「小さいからこそ輝く」自律(自立)した自治の実践と、地域の誇りを大切にしている自治の精神をこれからもしっかりと育んでいきます。
令和6(2024)年5月11日